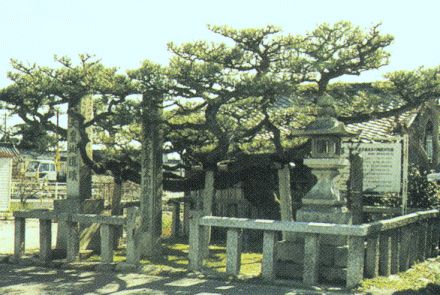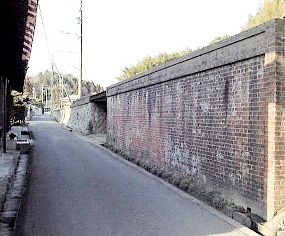|
山奥遺跡
◆所在地:四日市市大矢知町・羽津 |
|
蒔田城跡 ◆所在地:四日市市蒔田2丁目 |
|
藩校興譲館跡 ◆所在地:四日市市大矢知町 |
|
天武天皇迹太川御遥拝所跡
◆所在地:四日市市大矢知町1714 昭和16年5月21日県史跡指定 |
|
五島製糸場跡(亀山製糸五島工場) ◆所在地:四日市市垂坂町 |
|
旧大矢知村役場跡 ◆所在地:四日市市大矢知町1270 |
|
鏡ヶ池跡(笠取り池) ◆所在地:四日市市蒔田1丁目 |
|
大矢知山畑遺跡
◆所在地:四日市市大矢知町 |